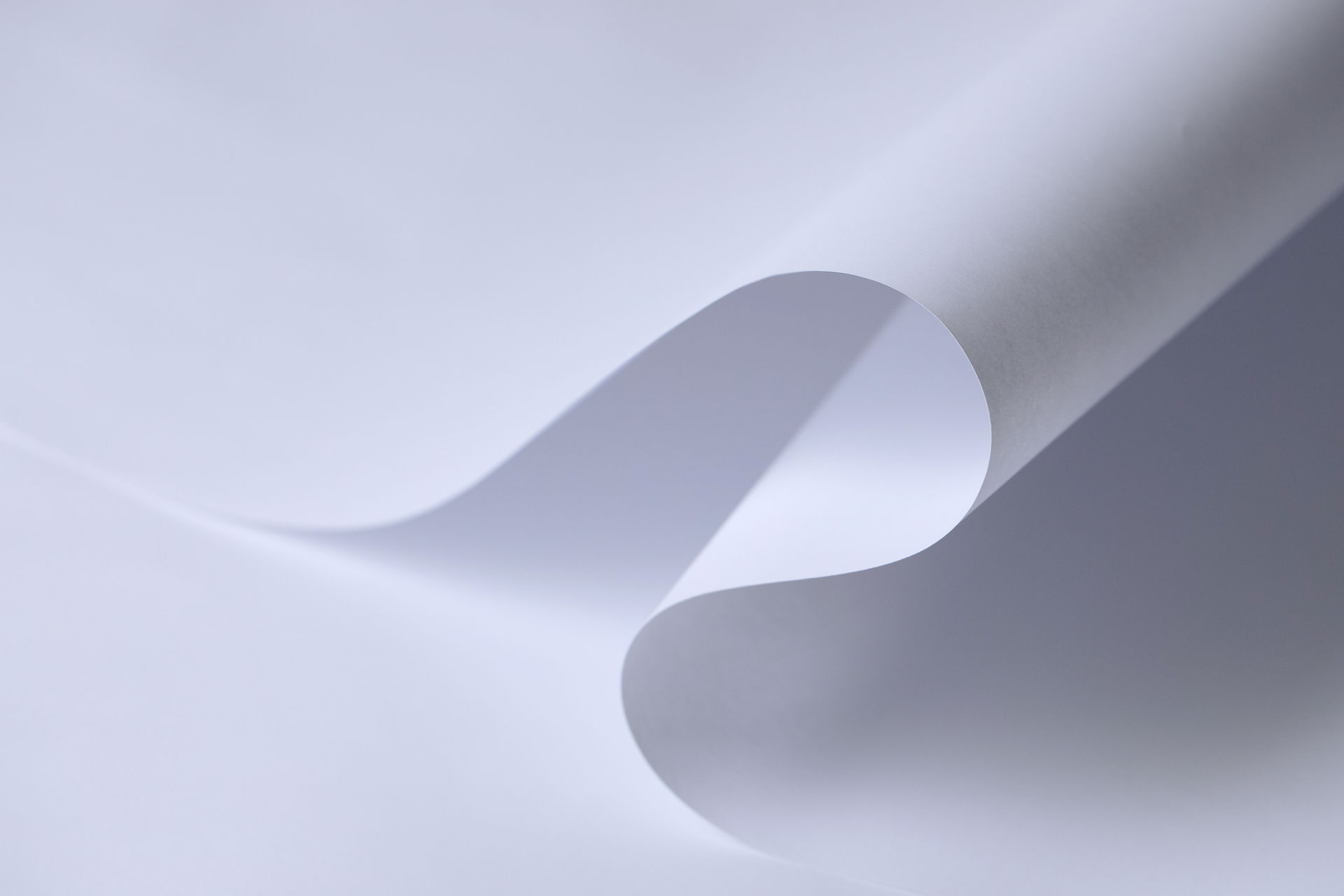

竹内淳 オフィシャルサイト
Jun Takeuchi

属和音〜主和音の奥深い世界 2
2 . V が I に進むとはどういうことか
最初に述べたように、V(ドミナント)は I(トニック)という全く性質の異なる和音に進むことが最も多いわけですが、それにあたり2つの段階が存在します。
1)ドミナント和音が鳴っているとき、和音自体に宿る力、勢い、重さ、独特の色彩を感じる段階(属和音の響きに対す
る意識。響きがイメージを産み出すことは、決してドビュッシーだけの専売特許ではない)。
2)その和音が次にトニックに進むことにより、横溢したエネルギーがトニックに収まり解消する意識を持つ段階(属和
音の機能に対する意識)。
1)でドミナント和音が鳴った瞬間にいろいろな思いが去来します。先ほど述べた「うずうずする、動きたくてたまらない性質」は、実はそれらのうちの1つに過ぎませんが、ドミナントを突き動かす確かな原動力になっています。そして2)の段階に進む訳ですが、一口にトニックに進むと言っても、トニックとの結び付きの段階は無数にあると言えます。それを仮に音量の差で3つに区分してみましょう。作曲家が譜面にどれくらいで弾いてほしいかを特に指定していない場合を想定します。
ア)ドミナントよりトニックの音量が弱く抑えられる。
イ)ドミナントとトニックがほぼ同じ音量で弾かれる。
ウ)ドミナントよりトニックが強く弾かれる。
このうち上記 2) の感じを最も端的に表しているのは ア)といえますね。平たく言えば、自ら動きたくてうずうずした性質のV が、I の和音に「収まる」、すなわちドミナントがトニックに「収まる」という感覚です。誤解を恐れずに言うならば、この、Vから I にかけて力が抜けたように感じること、結果として V の次にくる I は V より少し弱く聞こえることが、Vから I への最も自然な在り方と言って良いでしょう。(弱くなるとはいえその音量は、弾く人により毎回違って当然です。)
もちろん「収まる」ことは前提であり、全てではありません。それどころか、例外を楽しむような場面は山ほどあります。トニックに進む時、「収まる」ことを拒否する弾き方を求められることも多々あるし、収まることを「原則」に思っているからこそ、ここは収まらない、むしろ収めずに弾きたい、という欲求が(作曲家の側からも含めて)生まれてくるのです。そういうもろもろについては今後触れますが、まずはドミナントがトニックに収まるという感覚を実際に感じてみましょう。ドミナントがトニックに「素直に」収まる例です。
譜例2
大きな古時計(前半)

オーラリー(前半)

2曲とも、3〜4小節目、7〜8小節目にかけてのドミナント→トニックはいずれも、自然に、I の和音に収まるように弾くのではないでしょうか。I をV7 より少し抑えて弾く人が大半で、仮に I が V7 と同等の強さで弾かれることはあっても(「大きな古時計」は伴奏が収束する時が真の収束のため、例えば4小節目右手頭の音など収まらないこともあるでしょう)、それより強くなることは、ほぼないと思われます。このような、収まるように弾く意味とは何でしょうか?「フレーズを丁寧に切りたい、という気持ちの現れ」です。
ただし、あらかじめ申し上げておきますが、この感じ方ばかりでは、いつも I の和音に対してお辞儀をしているような、腑抜けの解釈になる恐れがあるのです。
やはり名曲は、そうなることを避けています。これらの曲の先を見てみましょう。
譜例3
大きな古時計 (後半)

オーラリー (後半)

「大きな古時計」も「オーラ・リー」も前半で 2 回にわたり完全終止が続きました。完全終止では I の和音に丁寧に向き合うのと引き換えに、フレーズの流れは止まってしまいます。そこで 2 曲とも後半8小節は盛り上げることで、次に来る完全終止までの「距離」を置いています。これによりフレーズに大きな流れが生まれ、16小節目の完全終止に円満に収まるのです。(なお「大きな古時計」は二部形式の曲では無いですが、ここでは構造上似た感じ方になるように切り取っています。)
調性の曲では、V → I がいろいろなところに置かれます。その場所が半終止や完全終止などであればフレーズの締めくくりになりますし、全くの通りすがりであれば力点を置かないかもしれません。完全終止の感じ方、また終止へのつながり方などを通して、解釈を広げられると良いですね。
なお解釈というのは、テンポ、メロディの音高や方向性、リズム、リズムパターン、アゴーギクやデュナーミク、フレージング、アーティキュレーション、そして和声の在り方、非和声音、伴奏の在り方、特に運動性、モチーフの在り方、声部間のバランス、楽器の音色、奏法の特徴、作曲家の様式、装飾音…などいろいろな要素を総合的に鑑みて行われるものです。ですからこの場では、和声に特化した解釈について考えていることになります。
何故和声に特化した解釈にこだわるのかといえば、音楽をメロディに留まらず立体的に語れるようになるための第一歩にしていただきたいのです。その意味で、V に対して I をどのように収めるか考えることは、価値ある一歩だと思います。
ここから先は、いろいろなV → I の在り方を中心に、他の和音も含めて見て行きましょう。